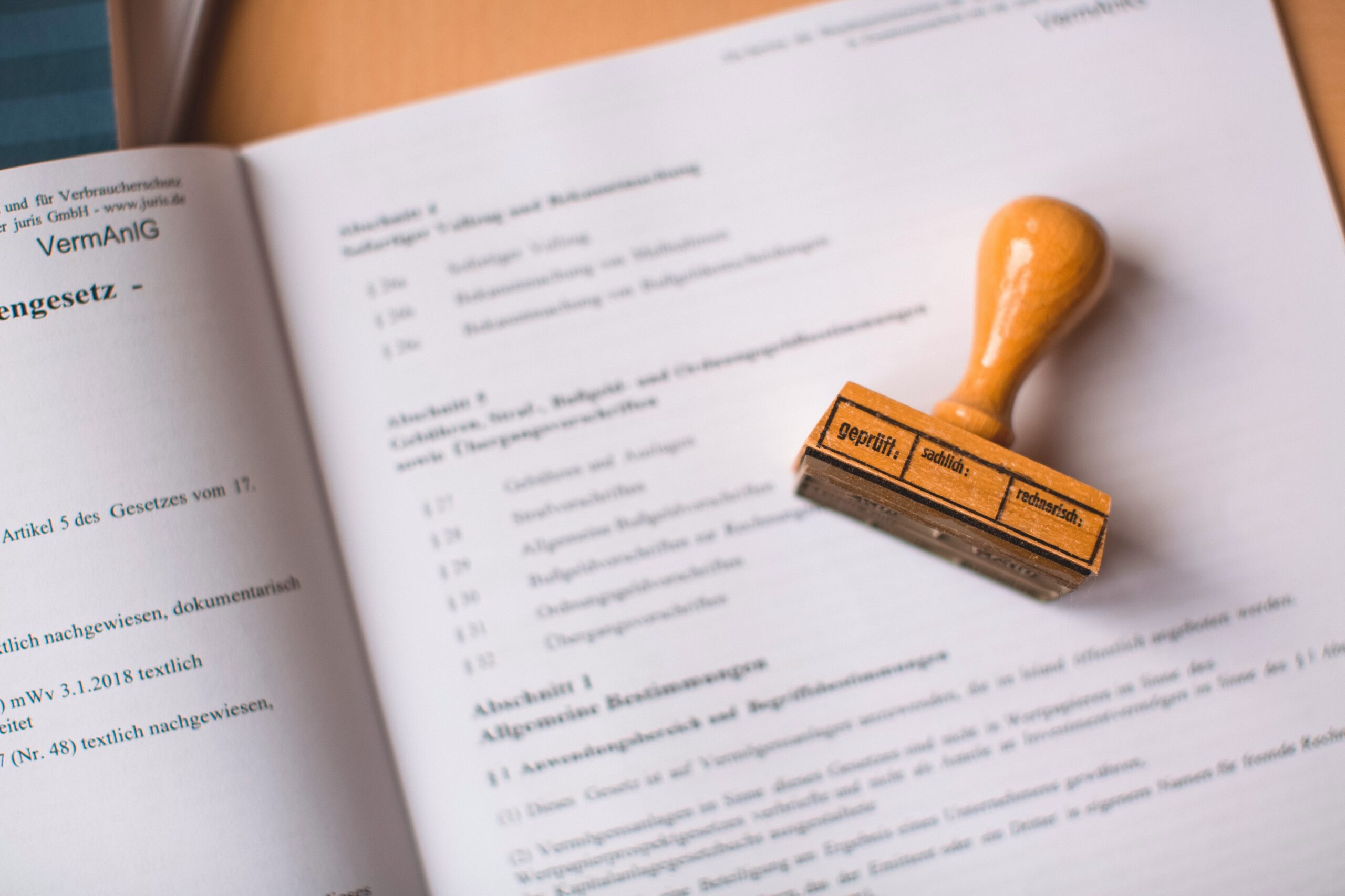こんにちは。グリー行政書士事務所 代表の酒井です。
再生可能エネルギーの拡大とともに注目されるのが 系統用蓄電池(BESS: Battery Energy Storage System)。
しかし実際に事業を進めようとすると、必ず壁となるのが 「許認可・制度・法律」 です。
- どんな許可や届出が必要なのか?
- どの法律に基づいて準備しなければならないのか?
- 自分の事業は「発電事業者」に当たるのか?
この記事では、これから系統用蓄電池を導入したい事業者の方に向けて、許認可・制度・法律を分かりやすく整理します。
系統用蓄電池に関わる主な許認可
1:都市計画法(開発許可)
- 市街化区域:比較的スムーズに設置可能
- 市街化調整区域:原則NG。ただし発電事業者設備として適用除外になる場合あり
👉 自治体ごとの判断が異なるため、事前協議必須。
2:農地法(農地転用許可)
- 農地を利用する場合は 農地転用(4条・5条) が必要
- 農振地区域なら農振除外申出から始める
3:建築基準法
- コンテナ型BESSが「建築物」とされる場合 → 建築確認申請が必要
4:消防法
- 一定規模以上の蓄電池は 危険物施設 とみなされる場合あり
- 防液堤や消火設備の設置など、安全対策が必須
5:環境関連法令
- 騒音・振動規制法(冷却ファンの音など)
- 景観条例(設置環境によって配慮が求められる)
- 大規模案件では環境アセスメントも
👉 許認可を軽視すると工事ストップのリスクにつながります。
系統用蓄電池と「事業者」の扱い
発電事業者としての位置付け
- 蓄電池を電力市場(容量市場・需給調整市場など)に参加させる場合 → 発電事業者設備として扱われる
- 系統連系を行い、電力会社の需給調整に資する場合 → 開発許可の適用除外になる可能性
小売電気事業者との違い
- 発電事業者は「系統安定化設備」を設置可能
- 小売事業者は「需要側のピークシフト」目的での利用が中心
👉 事業目的によって、求められる制度・許認可が変わります。
系統用蓄電池に関わる制度・法律の全体像
- 電気事業法
- 系統連系・技術基準・主任技術者の選任
- 都市計画法・農地法
- 土地利用規制
- 消防法
- 危険物規制、安全対策
- 建築基準法
- 建築物扱いの場合の確認
- 再エネ特措法(FIT/FIP)
- 既存の太陽光・風力と併設する場合、認定変更が必要
- 盛土規制法・河川法・道路法
- 工事規模によって追加の規制対象に
👉 制度や法律は縦割りで複雑に絡み合うため、横断的に整理できる専門家が必要です。
事業者が直面するリスク
- 許可が下りずに工事ストップ
- 農地転用の除外申請に時間がかかり補助金の締切に間に合わない
- 消防・建築を後回しにして追加工事費が発生
- 住民から騒音や景観について苦情 → 説明会や設計変更が必要に
当事務所ができるサポート
- 法令チェックと事前協議の代行
- 開発許可・農地転用など申請書の作成・提出
- 補助金申請と並行した法的整理
- 雨水計画・住民説明資料の作成代行
👉 許認可を一つひとつ個別に見るのではなく、「工事が止まらないための全体設計」を行うのが行政書士の役割です。
まとめ
- 系統用蓄電池の設置には、都市計画法・農地法・消防法・建築基準法など多岐にわたる許認可が必要
- 「事業者」の立場によって、制度や法律上の扱いが変わる
- 制度の理解不足は、工事中断や補助金不採択などのリスクにつながる
- 行政書士は、こうした許認可・制度・法律を横断的に整理し、設置をスムーズに進める伴走者となります
「自分の事業は発電事業者として扱われるのか?」
「この土地で系統用蓄電池を設置できるのか?」
👉 そんな段階からでもお気軽にご相談ください。
【無料相談】系統用蓄電池 設置許認可のご相談はこちら >>