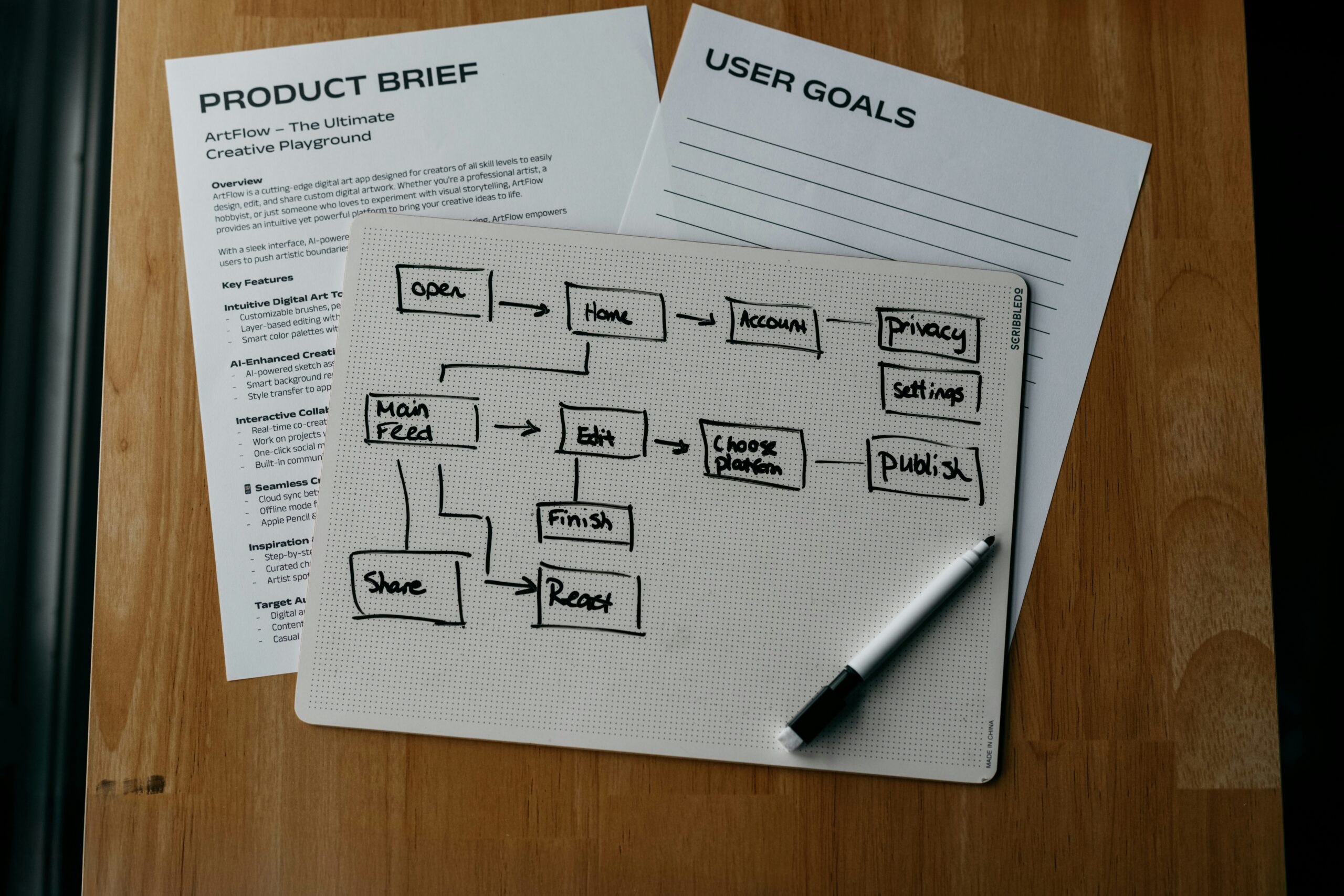こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所 代表の酒井です。
再生可能エネルギーの拡大に伴い、系統用蓄電池(BESS)の導入を検討する事業者さまが増えています。ところが最初の関門はいつも事業用地の検討。土地選びを誤ると、許認可が下りなかったり、工事費が膨らんだり、近隣との関係がこじれたり……。最悪、工事ストップにもつながります。
本記事は、これから系統用蓄電池を設置したい方のために、事業用地の選定ポイント・許認可・具体的リスクと対処を、行政書士の視点で分かりやすく整理した“保存版”です。
まず押さえるべき原則:良い用地=「通る・作れる・運用できる」
用地の良し悪しは、次の3観点で判断します。
- 通る:都市計画法・農地法などの許認可に適合するか
- 作れる:造成・雨水・アクセス等、施工が現実的か
- 運用できる:騒音・安全・災害・防犯面で持続可能か(周辺と共存できるか)
この3つを同時に満たす用地が“良い用地”。どれか1つでも欠けると、のちのち大きなリスクになります。
机上スクリーニング(一次ふるい):まず机でここまで確認
1. 都市計画・区域区分
- 市街化区域/市街化調整区域(調整区域は原則NG。例外・適用除外の余地を要確認)
- 用途地域・地区計画、風致・保全などの指定の有無
- 自治体の開発指導要綱・34条運用(基準や付条件)
2. 地目・農業振興地域
- 地目が農地なら**農地転用(4条・5条)**が必要
- 農振地区域は農振除外から。青地は特に難易度高
3. ハザード・地盤
- 浸水・洪水・内水・土砂・液状化・高潮・津波のハザードマップ
- 公共地盤情報・既往の湧水履歴 等
4. 周辺用途・保全指定
- 学校・病院・住宅密集地・景観計画区域・自然公園・鳥獣保護区 等
5. アクセス・道路条件
- 設備搬入向けの接道・幅員・高さ制限、ルートの曲がり
- 工事車両の離合、安全確保
6. 系統連系の可能性
- 近傍の変電所・配電線、連系ポイントの有無
- ルート上の地役権・占用の見込み
7. 文化財・インフラ埋設
- 埋蔵文化財包蔵地の該否(該当なら届出や調査の可能性)
- 既設の上下水・ガス・通信等の埋設有無
机上で赤信号が出る用地は、原則として深追いしません。次の候補へ。
現地確認(二次ふるい):図面では分からない“実態”を見る
- 地形・勾配(造成量の見積もりに直結)
- 湧水・ぬかるみ、既存側溝の流下状況
- 隣地境界・越境、既設工作物(法面・擁壁)
- 騒音源と感受性施設(住宅・学校・病院までの距離)
- 塩害の兆候(海岸近く:金属腐食、塩害樹木)
- セキュリティ(見通し、侵入容易性、夜間環境)
- ケーブルルートの障害(跨道・渡河・私有地の交渉要否)
現地で“想定外”が出やすいポイント。写真・動画・簡易測量で証拠化しておくと許認可・設計がスムーズです。
許認可の見立て:法律上の観点から見る
都市計画法(開発許可/適用除外)
- 調整区域は原則開発許可が必要
- ただし発電事業者の系統安定化設備として適用除外を主張できる場合あり
- 自治体運用差が大きいため、都市計画課との事前協議はマスト
農地法(転用)・農振除外
- 農地は4条・5条許可、農振は除外申出から
- 青地・高生産性はハードル高。別地検討も視野に
建築基準法(建築物該当性)
- コンテナ型BESSが建築物扱いとなるケースあり → 建築確認の可能性
消防法(危険物)
- バッテリーの種類・容量により危険物施設の扱い
- 防液堤・自動消火・防爆等の計画要求
雨水・造成・盛土
- 面積が大きいと雨水計画が必要(貯留・浸透・透水性舗装 等)
- 盛土規制法の対象規模かの判定
環境・景観・騒音
- 景観条例・騒音振動届出・(規模により)環境アセスの要否
実務は横断管理が要。どれか1つ遅れると全体が止まります。行政書士は手続きの順序設計と事前協議でリスクを最小化します。
近隣・環境配慮:事前に“説明できる設計”を
騒音(ファン・PCS・EMS)
- 想定レベルに応じ離隔確保、防音壁、夜間運用の工夫
- 予測値と根拠(計算条件・設置高)を見える化
近隣への影響
- 住宅・学校・病院等からの視認性
- 植栽・外構・カラーリング等の景観配慮
水害・塩害
- 浸水可能性には嵩上げ・排水経路の確保
- 塩害が想定される海岸近くは、材料選定・防錆計画
セキュリティ(盗難・侵入)
- カメラ・照明・柵・通報システム等の防犯設計
- 無人運用前提の点検・巡回計画
住民との直接交渉・合意形成の代理は行いませんが、当事務所では住民説明会の資料作成代行までサポートします。
系統連系:距離と経路でコストが激変
- 近傍の連系可能容量、電圧階級、保護協調の前提
- ケーブルルート上の地役権・道路占用・河川横断の要否
- 伐採・掘削・占用に伴う許認可の重なりに注意
“近いから安い”とは限りません。 ルートが私有地を横断する、橋梁を越える等で一気に難度が上がることがあります。
ここでつまずく!用地選定の“あるある”失敗とリスク
| 失敗例 | 起きがちな結果 | 予防策 |
|---|---|---|
| 「発電事業だから開発許可は要らないはず」と着工準備 | 行政から工事中断の指導 | 事前協議で適用除外の可否を明文化、同時に許可ルートも用意 |
| 農振・青地を甘く見る | 除外・転用が進まず計画停滞 | 初期に農地属性を精査、別地オプションも |
| 雨水計画を後回し | 設計差し戻し・外構再設計 | 開発要綱準拠の計算・図面を早期に |
| 建築・消防の見落とし | 追加設備・再申請 | 建築物該当性と危険物を最速で判定 |
| 連系ルートの地役権未確保 | ルート変更・コスト増 | 経路の地権者整理を机上段階で |
| 住民配慮不足 | 苦情・説明会やり直し | 説明資料で安全・景観・騒音対策を可視化 |
| 防犯軽視 | 盗難・侵入 | カメラ・照明・柵を計画段階で組み込む |
事業用地スコアカード(初期判断の型)
各項目をA/B/Cで簡易評価し、Aの多い用地を優先します。
- 許認可適合性(都市計画・農地・条例)
- 系統連系距離・経路
- 造成難度・雨水対策の負担
- 災害リスク(浸水・土砂・塩害・液状化)
- 近隣への影響(騒音・景観・交通)
- アクセス(搬入動線・幅員・重量制限)
- セキュリティ確保のしやすさ
- 工程の確度(事前協議の見通し)
スコアの悪い箇所は設計・手続きで補えるかを検討し、それでも難しければ早めに撤退判断を。
当事務所ができること
- 法令・要綱の棚卸し(都市計画・農地・建築・消防・環境・雨水・盛土 ほか)
- 役所・電力会社との事前協議(論点整理資料の作成・同行/代理)
- 開発許可・農地転用 等の申請書作成・提出代行
- 雨水計画・騒音説明 等の添付資料整備(設計士と連携)
- 住民説明会資料の作成代行(※直接交渉・合意形成の代理は行いません)
- 補助金と許認可の並走設計(申請要件の満たし方を整理)
目的はシンプル。工事ストップを防ぐための“順序設計”と許認可が“通る資料”を用意することです。
まとめ:良い用地は「最初の1か月」で見極めがつきます
- 机上スクリーニング → 現地確認 → 事前協議の三段構えで、通る見込み・コスト・工程の確度が見えてきます。
- 系統用蓄電池の事業用地の検討は、許認可・施工性・運用性の3つを同時に評価するのがコツ。
- 不確実性が大きい土地を抱え込むより、早い見切りと次候補の打診が結果的に近道です。
「この土地、進めて大丈夫?」という段階からご相談ください。
系統用蓄電池の設置がスムーズに進むよう、行政書士として伴走します。