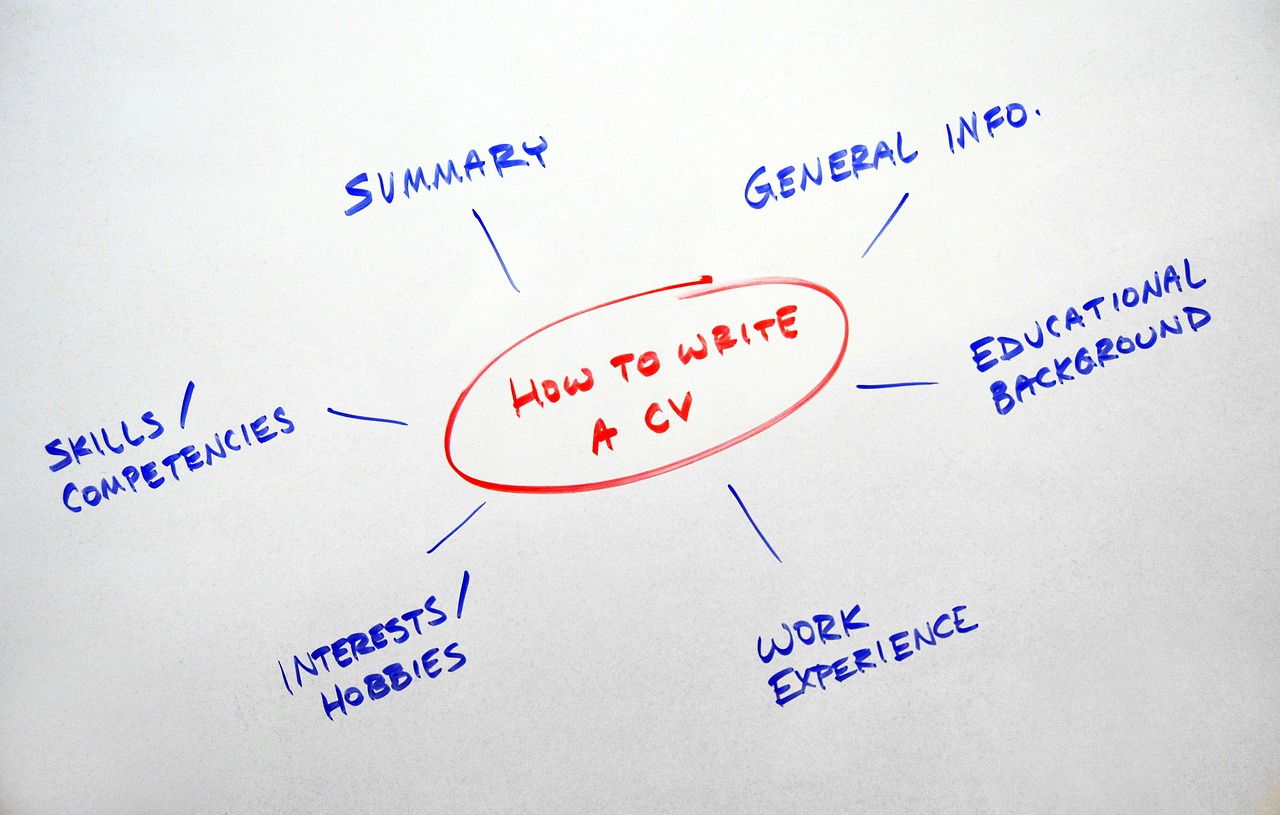こんにちは。グリー行政書士事務所 代表の酒井です。
再生可能エネルギー事業が拡大する中、注目されているのが系統用蓄電池(BESS)です。
太陽光や風力など再エネ電源の変動を吸収し、電力系統の安定化に不可欠な存在となっています。
しかし、実際に「系統用蓄電池を設置したい」と思っても、
- 設置の流れが複雑でよく分からない
- 許認可の種類が多くて不安
- 行政や電力会社との調整が大変
といったお悩みを抱える方が多いのではないでしょうか。
本記事では、系統用蓄電池の設置から運用開始までの流れを整理し、どの場面で行政書士がサポートできるのかを丁寧に解説します。
系統用蓄電池設置の基本的な流れ(全体像)
系統用蓄電池プロジェクトには、大きく次のようなステップがあります。
- 用地の選定と取得(関係者:地権者・自治体)
- 電力会社との協議(接続可能性の確認)
- 地元調整・自治体確認(地元住民への説明含む)
- 機器・施工事業者の選定(メーカー・EPC)
- 各種申請手続き(市場・法令関係の申請)
- 収益性の判断(事業採算性の確認)
- 資金調達(金融機関との調整)
- 許認可の取得(都市計画法・農地法・消防法など)
- 補助金の申請(経産省・自治体の制度を活用)
- 保険の設定(火災・災害リスク対策)
- 土地造成(造成計画・雨水対策)
- 設置工事(EPC施工・電気工事)
- 系統連系工事(電力会社との接続)
- 運用開始後のO&M契約(保守・管理)
- 市場運用・収益化(容量市場・需給調整市場など)
👉 つまり、単なる「機器を置く」だけではなく、土地・法令・住民・金融・補助金・施工・市場取引まで、幅広い調整が必要です。
設置に必要な主な許認可とチェックポイント
都市計画法(開発許可)
- 市街化区域は比較的スムーズ
- 市街化調整区域は原則NG → ただし「発電事業者設備」として適用除外になる可能性あり
農地法(農地転用)
- 農地利用には4条・5条の農地転用許可が必要
- 農振地区域は農振除外申出からスタート
消防法
- 大型蓄電池は危険物規制の対象になることがある
- 消火設備、防液堤、防爆対策が求められるケースも
建築基準法
- コンテナ型BESSが「建築物」にあたる場合は建築確認申請が必要
雨水計画・盛土規制法
- 面積1,000㎡を超えると雨水計画が必須
- 盛土規制法に基づき、造成規模によっては追加許可が必要
補助金との関係
令和7年度も、経済産業省や東京都などで系統用蓄電池の補助金制度が整備されています。
ただし補助金は、事業計画や許認可の整備が前提となることが多く、許可が揃わないと採択されにくいのが現実です。
当事務所がサポートできること
系統用蓄電池設置の流れは多岐にわたり、事業者さまが単独で対応するのは大変です。
行政書士は、次のような場面で力を発揮できます。
- 法令調査と事前協議(都市計画課・農業委員会・消防・環境課など)
- 各種許可申請の書類作成・代行
- 補助金申請に必要な法的整備
- 雨水計画・住民説明資料の作成補助
- 手続きの順序設計(工事ストップを防ぐ工程管理)
👉 許認可を横断的に整理し、自治体や電力会社との調整をスムーズに進められるのが強みです。
まとめ
- 系統用蓄電池の設置には「土地・系統接続・許認可・資金調達・工事・市場運用」まで幅広い流れがある
- 特に都市計画法・農地法・消防法・雨水計画などの許認可が重要
- 誤ると工事ストップや補助金不採択のリスクがあるため、行政書士による早期サポートが安心
「この土地で本当に設置できるのか?」
「開発許可や農地転用は必要なのか?」
👉 初期段階の疑問からでもお気軽にご相談ください。